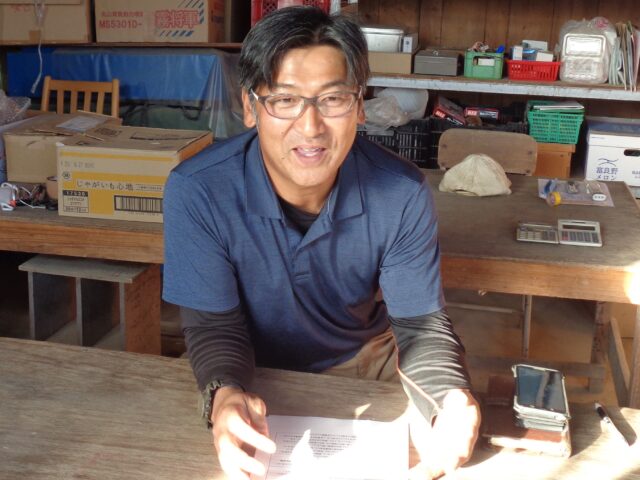自分の責任で自由に、結果は経営に 🍅野菜
自分の責任で自由にできる、その結果がすぐに経営に表れる ~ 農業っていいなぁ
[Kさん(45歳)、平成28年4月就農、月形町]
(取材:令和2年10月13日TC記、協力:月形町農業担い手育成センター)

地域の概要
月形町は、北海道空知管内の南西部に位置している、人口3,100人、農耕地約3,000㌶、農業が基幹産業の町です。
町の北東部は丘陵地をなし、花き・果菜等の集約的農業に適しており、町の中心部は集約的農業と土地利用型農業とが混在しています。南部は石狩平野の一部になっており、米麦・豆類の栽培に適し土地利用型農業が展開されています。
月形というと、花きが思い浮かびますが、その他にも、水稲、麦・大豆類、野菜(メロン・カンロ・スイカ・かぼちゃ・トマト・ミニトマト)なども盛んです。
月形町は、平成6年度に新規就農の受入制度を創設以来、19世帯を受入し、うち16世帯が地域に定着しています。その殆どは花き専業農家ですが、最近では野菜で就農する参入者も増えています。
動機から就農まで
ご夫婦とも元は銀行員でしたが、農業には以前から興味があったと言います。40歳を目前に、再度農業にチャレンジしたいと思い、まずは(他の町でしたが)農業体験に入りました。その後、北海道農業公社の就農情報を元に、5,6カ所の候補地を回り、月形町に就農を決めました。
その理由は、実習農場の敷地内に住宅が有り、保育園も近く子育ての環境が良かった事だと言います。また、先輩参入者が多く長く営農しているのは、町のサポート体制が整っているに違いない、「月形は続けてやっていける町」という判断が、kさんの背中を押しました。そして、札幌に近い事も、パートナーを説得するのに好条件でした。
反面、「農地探しは苦労するぞ」とも言われたそうです。農地取得については、月形町、知人、研修先の親方が、力を貸してくれました。農地の賃貸リストを貰い、何カ所か回りましたが手詰まりになっていた時に、今の就農地の地主さんと顔を合わせる事があり、就農地がまだ決まらず困っている事を話したところ、「いいよ、譲ってあげるよ」と言って貰えたのです。
こうして平成28年4月、「逆境に立たされている業種だからこそやってみたい」というKさんの想いが、「就農」という形で実現しました。
経営規模(令和2年)
所有地 0.9ha (田 0.8㌶、畑 0.1㌶)
ミニトマト 11a・2棟
カンロ 10a・2棟
フルーツトマト 5a・1棟
かぼちゃ 36a (ハウスの間で栽培)
施設 ハウス 5棟(87m)
育苗ハウス 1棟
倉庫 1棟
機械 トラクター 2台
トラック 1台
防除機 1台
労働力 本人、パートナー、両親(主に母が年間100日ほど手伝いに来てくれる、力仕事の場合は父)
生産実績 ミニトマト 6.6t/10a カンロ 3.8t/10a
かぼちゃ 0.9t/10a フルーツトマト 2.3t/10a
販売 100%JA出荷
住宅あり
就農支援制度の活用
農業次世代人材投資資金(準備型を夫婦で)
農業次世代人材投資資金(経営開始型を夫婦で)
月形町新規就農者等招致促進事業 (新規就農実習生、新規就農者)
後輩へのアドバイス
・町内や周囲の農家とコミュニケーションをとり、受入られることが大切。
・最初は、一般的な生産設備を整え、その後少しずつ改善を継続する。
・農業者は経営者であることをしっかりと認識し、農業で家族を支えるという自覚を持つことが大切。
・営農計画、作業計画、資金(返済)計画を立て、P(計画) D(計画を実行) C(行動を評価) A(改善し次回につなぐ)サイクルを回す。
経営の方向性
就農した頃は大玉トマトでしたが、現在の経営の主力はミニトマトになっています。個選共販の大玉トマトでは経営が厳しいと判断し、どうしたらいいのだろうと悩んでいた時に、農協や農業改良普及センターからヒントを貰い、就農3年目に、共選の選果場のあるミニトマトに切り変えました。
今では、5月定植のミニトマト2棟と、カンロの収穫を6月中に終わらせ、その7月にミニトマトを植え、単価が上がる9月から収穫が始まるといった、2棟を組み合わせる形が出来上がりました。
疑問を持ちながら行っていたかん水や追肥のタイミングも、生育環境測定装置を活用する事で、ミニトマトの反収を3割近く上げる事ができました。この技術は、もう1年続けてみて自信を付けたいと言います。
「今後は農地面積次第です。農地の拡充を希望しており、拡充ができれば人を雇用する事や、近隣農家との協力体制も視野に入れていきます」
雑感
中小企業診断士の資格が、今の経営に活かされている事は言うまでもありません。また、地元農業改良普及センターや中央農業試験場の試験用に場を提供するなど、指導機関とも密接な関係を築き、いち早い情報収集や活用にも心掛けています。
就農して良かった点は、家族との時間がしっかりとれる事、自分の責任で、労働時間や設備投資が自由にでき、その結果がすぐに経営に表れる事だと言います。
就農を目指す時に、パートナーからは「生活できないと辞めるから」と言われていたそうです。
就農後7回目の収穫を終えた今、「農業を始める意味は、先ずは作物がしっかり穫れることが大切」という初志が実現し、「何とか農業を続けていけるかな」と安堵している、Kさんの少し日に焼けた笑顔がありました。